
【今回の質問】
「子どもの気持ち」を尊重したく、親としての関わりの線引きが難しいです。
親:「そろそろ宿題しない?」
子:「まだ、後で」
親:「わかった…」
親:「本を読んだらどうかな?」
子:「今、そういう気分じゃない」
親:「そうなのね…」
子どもの気持ちを大切に、と思っていると、
「やりなさい!」という言葉が言いづらくなり、
結果として、子どもの言いなりになってしまいます。
理想の子育てを追求すると、
言いたいことが言えなくなるという
ジレンマを抱えてしまいます。
子育てに関する知識が大きく膨らんだ今、
子どもにどこまで言っていいのか、
自分なりの線引きの仕方について
考えてみましょう。
【目次】
子どもの気持ちの尊重の大切さ・難しさ
自分なりの「線引き」に向かう3つのポイント
「加減」をみる
仕掛けを工夫する
子どもに聞いてみる
◆子どもの気持ちの尊重の大切さ・難しさ
「なぜ、子どもの気持ちの尊重が大切なのか」、
この問いにシンプルに答えるなら、
子どもも人格を持った一人の人間だから。
大人の未成熟な状態ではなく、
子どもは子どもとして生きているから。
こんな答えが浮かびあがってきます。
しかし、近年特に「子どもの気持ちの尊重」が
問われるようになった背景には、
子どもの尊厳以外に、
社会の急速な変化もあるように思います。
例えば、学習指導要領では、
「主体的・対話的で深い学び」が大きなテーマとして掲げられ、
その実現のために、
「知識及び技能」
「思考力・判断力・表現力」
「学びに向かう人間性等」という、
3つの柱が示されるようになりました。
不透明な時代を生きる子ども達には、
「自ら」考え、「自ら」行動していくことが重要ということです。
このような流れを受けて、
「子どもの主体性や自主性」を尊重することの大切さが、
ますます重視されるようになってきました。
親がレールを敷くのは違うと思う。
子どもの気持ちを尊重して、
子どもが好きな道を見つけて進んでいくことを応援したい!
このような家庭が増えてきているということです。
しかし、子どもの気持ちを尊重し、
必要なサポートを提供する…、
理想的なこの子育て観には、難しさも伴います。
「子どもの気持ち」と「親の願い」にはズレがあるからです。
子ども任せにしていると、親の望む方向に進まないこと、
求める結果まで到達できないことが、
親の心を悩ませます。
◆自分なりの「線引き」に向かう3つのポイント
もちろん、子どもの年齢によっても、
一人ひとりの個性によっても、
「親がどこまで関与するか」は変わってきます。
「どこまで子どもの意見を受け入れる?」に対しても、
「このくらい」という基準はなく、
状況に応じて自分で決めていくしかありません。
自分なりの「線引き」に向かうためのポイントを
3点ご紹介します。
▶︎▷「加減」をみる
例えば、お風呂に入る時の湯加減、
皆さんはどのように「ちょうど良さ」を見つけていますか?
恐らくお湯に手入れて、熱ければ水を足す。
冷たければもっと沸かす。
実際に触ってみて(試してみて)、
その後調整していらっしゃることと思います。
子どもへの関わりに関しても、
湯加減のように、
実際に触ってみて(試してみて)が
機能するように思います。
最初から白黒はっきり決めてしまうのではなく、
まずは子どもの言い分を受け入れてみる。
そして様子を見て、
「これではよくない」と判断するなら、
親側の意見を取り入れる。
あるいは、
「私の考えとは異なるけど、子どもの考えに任せてもよさそう」と思えるなら、
多少のうまくいかなさはあったとしても、
子どもの主張を通すようにする。
試してみて、その後修正。
あえて「線引き」を決めずに、やりながら決めていく。
これなら、ストレスなく
子どもの気持ちの尊重に向かっていけそうです。
▶︎▷仕掛けを工夫する
子育てで大切なのは、環境づくりです。
子どもが「気持ちを切り替える」、
そんな仕掛けを作ってみませんか。
どこまで関わったらいいのか、と考える以前に、
子どもの気持ち自体を切り替える工夫をするということです。
例えば、子どもの「好き」に焦点を当てます。
サッカーが好きな子なら、
「プロサッカー選手の話が載っているよ」と
選手が発信する記事(本)を見せてみます。
ふっと気分が変われば、
「本を読みなさい」
「嫌だ」
のやり取りなく、
子どもは本を読んでいるかもしれません。
体を動かすことも、
気分を変えるための良い仕掛けになります。
「宿題をする前に、ストレッチしようか」と誘います。
実際に体を動かすことで
宿題スイッチが入ることもあるでしょう。
線引きに悩んだら、
子どもが自ら動き出すための仕掛けを探してみる。
こんな工夫が役立つ時もあるでしょう。
▶︎▷子どもに聞いてみる
子どもの意見を受け入れるか、自分の意見を通すか…。
そこで、悩んでしまうのなら、
実際に子どもに聞いてみてはどうでしょう。
他者とともに生きる社会には、
対立する意見があるのは当然のこと。
無理に合わせようとしたり、
無理に変えさせようとするのではなく、
「お母さんはこう思うんだけど、どうしたらいいかな」と、
子どもの意見を聞いてみます。
社会性を身につける、よい機会にもなりそうです。
突然の質問に子どもが答えられないこともあるでしょう。
あえて答えないこともあるかもしれません。
そんな時には、横に座ってみてください。
子どもの様子を横から眺めていると、
言語化されない子どもの気持ちが見えてきたりするものです。
自分の思いを丁寧に伝え、
子どもの気持ちも丁寧に汲み取ってみる。
こんな関わり合いの中で、どこまで関与するか、
最適な線引きのラインが見えてくるように思います。
記事執筆
江藤真規
https://saita-coordination.com/



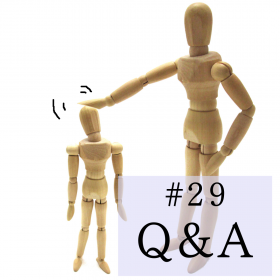



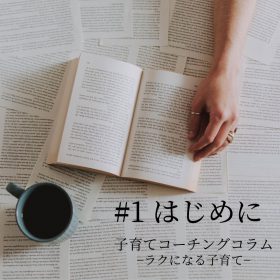


この記事へのコメントはありません。